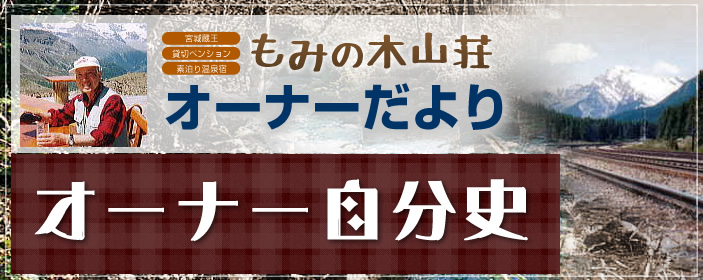第1話 イジメられっ子
その1 開戦から疎開まで
俺は1932年9月1日に生まれた。 その9月1日に意味がある。
1923年の、この日関東大震災が起きたのだ。
当時の話では死者は15万人といわれた(今では10万5千人が正解)大変な日に生まれた。
当時の情け深い日本国民は首都圏に起きた地震の悲惨さを語り継ぐ追悼の日だ。
我が誕生日も震災をしのんで非常食おにぎりだけ、ケーキなんかない、そして震災の話を繰り返し聞かされた。
母はどこからからの帰り道、材木屋の前で津波のようにたおれ覆いかぶさる材木を危うくかわし、泣きながら帰ってきたそうな。
当時住んでいた東京の小石川(今の文京区西部)はなぜか材木屋多かったそうだ。
母の父、俺のじぃじは当時満州(いまの中国北部)で満州鉄道の車両を作る大工だった。
それが宝くじの1等に当たり、匪賊(満州の強盗団)に襲われると、急きょ東京に、そしてその金で小石川に9軒の貸家の家主となったのです。日本での宝くじの発売は戦後だが、当時の満州国では宝くじが発売されていた。
宝くじって本当にあたるのだなー!当たったら黙っていればいいのに。
しかし満鉄の大工仲間、一緒に買ったのも知っているし、せまい交際範囲、ニタついた顔のジィジ。
すぐばれてしまったそうだ。強盗団に襲われて殺されるか、仲間にたかられるか、
逃げるように東京に来たことは大正解であった。
この9軒の貸家はどうなったか、いきさつはよくわからないが、俺が生まれた頃は東京中央線荻窪駅のすぐそばに6軒の貸家の大家となっていた。
兄貴は小石川生まれ、江戸っ子だ!、お前は荻窪の田舎生まれだ。とよくケンカの
ネタにされた。
俺は荻窪生まれのガキ大将の悪[アク]である。
誰がつけたかはっきりしないが、いじめられっ子から、たくましいガキ大将になった時いつの間にかついたアダ名である。
百姓の労働で鍛え上げられたレスラーのような体格の俺に文句などつける奴がいなくて、しかも爆薬など作る方法を子供ながら知っていたので皆恐れていたようだ。
黒色火薬に赤燐を混ぜ角のある小石を入れ、きっちりと和紙で固めた丸い花火は投げると爆発して皆を驚かした。(少し小さいのはかんしゃく玉という名で駄菓子屋などにあるおもちゃ花火)
中学校などではカンニングの元締めをして幅をきかしていたが、本当はいたずらが好きな悪がきの集まりです。
1941年12月8日突然アメリカと戦争を始めたと、聞かされた。小学2年のときだ。
俺のおやじは飲んべーの船乗りであったが、さすが世界をまたにかけた男、戦争が始まり、日本が勝った勝ったのチョウチン行列に浮かれていたとき、すでに、やがて東京は大空襲となり、日本は負けると言っていた。
まだ日本が真珠湾の奇襲などで勝ち進んでおり誰もが考えていない開戦半年後の父の予感だ。しかしこの様なことを言えば国賊扱いになりかねない時代、父に口止めはされた。
我が家は荻窪駅のそば、鉄道は攻撃目標となり爆弾の雨が降ってくるそうだ。そこで俺達一家は新潟に在る父の実家に疎開することになった。この時俺は小学3年、開戦して1年余りでこんな予測が出来る父、すごい先見の明と今は思う。
疎開のことを実家の兄に頼み、笑顔一つ見せずこわばった顔で電車に乗って行った父の姿は強烈な印象となって残った。
疎開とは都会が爆撃されるので田舎に避難することである。先見のきく親父、。船乗りとしてたびたびアメリカに荷物を運びその工業力などを熟知していたのだ。
父を尊敬した理由は
それは戦争がはじまる前であったから小学校1~2年生の頃だと思うが、親父の乗っている貨物船(N商船の最新鋭貨物船で会社では一番大きい舟だそうだ)を見せてもらってからである。
父はこの船の機関長でチエンチャー(チーフエンジニアの略称の様だ)と呼ばれていたのを覚えている。
その機関室は巨大なジーゼルエンジンのシリンダーが左右にズラリと並びその動力は一抱えもあるスクリューシャフトを回すのだ。
スクリューシャフトは船尾で船体との間から水が少し噴出していたのを鮮明に覚えている。水漏れで船が沈まないのか聞いたら、船は大波で揺れるとき隙間がないとスクリーユーのシャフトが曲がり軸が焼き切れるということ、こんなに太いのに曲がる?大波を想像できずびっくりした。
多くのでかいメーター、計器の数々、それをつなぐギラギラ輝く銅パイプの束、父はコレを見張っている。でも耳がたよりでエンジン音がおかしいときに見るぐらいだそうだ。
後で見せてもらった船長の操舵室も見たがメーター類も少なく貧弱で、巨大な機械を沢山のメーターを読みながら動かす機関長の親父のほうが、船長よりえらいと思った。
当時小学生の兄も同じ思いのようで、大学では内燃機関(ジーゼル)を専攻して、卒業後はHジーゼルを受けたが戦災で工場の大半を失ったHジーゼルは採用も少なく兄は入社を失敗した。
でも兄からいつもジーゼルエンジンの原理など聞かされて子供心に理科系を目指すようになったのだ。
親父の船の見学は楽しかったが戦争が始まると何処に親父の船がいるかは秘密になり、見学などさせられず戦争はやだと子供心にも思った。
戦争が始まってから一回だけ家に帰ってきた親父は寡黙で笑顔さえ消え別人のように怖い顔であった。
きっと父は生きて帰れないと思っていたに違いない。バンサイの声で送られる軍人と違って、大切な物資を運ぶ船員の動きは秘密であり、近所、友人の見送りすら許されないのだ。
船乗りの宿命、家に居ることも少なくいつも海の上の父。そしてたまに家に帰ってくるといつも酒を飲んでいる父。俺は他の家庭のように父にベタベタという感情は少ないが、尊敬の念はあった。
それは荻窪にいたころの小学一年ぐらいのとき、学校帰りに一台のテーブルを担いでいた行商のオッサンにであった。どこかで遊んで帰ってみると、あの行商のオッサンの担いでいたテーブルを座敷で嬉しそうに撫でている父の姿をみた。
仲良しの東はすぐ近くにある家具屋だ。そこで買えばいいのに、と俺は言った。しかし父は少し高くても、苦労して歩く行商から買えば、喜んでもらえると言った。
そういえば当時行商が盛んで、千葉あたりから山のように海産物を担いでくる行商のオバサンからよく魚の干物などを買う父を見た。父は弱者にやさしいところがあって、俺はそんな父に好感をもっていた。
今は世の中が悪くなり、訪問販売は詐欺的なものも多く油断ならないが。
このテーブルは今では素朴なものだが、荻窪から戦時中の疎開先新潟、父の実家和納村に持って行き、さらに新潟市の簡易住宅で終戦を迎え、そして東京の小金井市に引っ越した時も附いてきた。
なんか因縁を感じるテーブルで、俺は結婚して八王子に持ってきた。そしてこのテーブルはなんと五回の引っ越し、七十数年経つ今終の棲家の仙台南部、桜の名所モミの木は残った原田甲斐の古城跡の船岡の家にある。
一時物置に保管したとき虫に食われた部分を自分で治したぼろテーブルになったがまだ使っている。テーブルを見るとあの父の姿を思い起こすからだ。
その2 新潟へ疎開
父が海の戦場に行ったあと、間もなく叔父が、我が家を実家へ疎開させるため、上京してきた。叔父はあまり引っ越しの手伝いもせず、父の残して行ったカメに入った焼酎を毎日朝から飲んでいた。
母はひとりで一生懸命に荷物をまとめていた。そんな叔父を子供心ながらこいつ何しに来たのかと俺は思った。
でも俺と兄貴とは一生懸命に母の手伝い、衣類など少し高級なものは柳こうりと言って竹の柔らかいような素材の箱に詰め込み、シャツなどはズックの布でできた袋にせっせと詰め込んだ。
今で引っ越しの定番段ボールはこの時代にはなかった。
学校で皆にお別れの挨拶をしたが、まだ疎開など珍しくまるで探検に出かけるようで得意になっていた。恐ろしい、いじめが待っているのも知らずに。
やがて荷物も送り、上野から夜行列車に乗り新潟へと向かった。
昭和十七年の早春、俺が小学校三年の時であった。
長岡で列車を乗り換えたローカル線は、車内で赤々と石炭ストーブが燃えていた。
暖房に火のついたストーブが車内にありびっくりした。、東京では目にしない初めて見る光景だ。
初めて聞く車内で語られる重たい調子の方言に、別世界に来たような気がした。
車窓から見た雪で純白の弥彦山が朝日でオレンジ色に輝き、とても美しいと思った。
駅に降り立った俺は東京には無い朝の冷気に、北国に来たな、と身の引き締まる思いがした。着いた所は新潟市より汽車で一時間程の和納村という農村である。
父の実家は昔、醤油の製造販売を行なっていたそうで、太く黒い梁に支えられた天井からなるだだっ広い土間と、大きなイロリのある広間、そして多くの部屋が、狭い東京の家に住んでいた俺をびっくりさせた。
叔父は一生仕事もせず、この身代を飲んで潰した幸せものである。
俺達一族は呑んべいの血筋があるようだ。
和納村はどこまでも水田が続き所々に島のように木が茂っている所が村である。今のように、むき出しの家など無く、家は林に囲まれて自然と一体となっていた。
しかし風景の、のどかさとは裏はらに、俺は学校で徹底的な、いじめにあった。この頃はまだ疎開などなく、まあ疎開のはしりであった。都会から来た青白いもやしの様な俺は、絶好のいじめのタ‐ゲットとなった。
どういういじめにあったか、全部は覚えていないが、俺が鬼になり、皆で鬼を追いかけ、取り囲み蹴飛ばすという、まあ俺が、フットボールのボールになったようなゲームが一番ひどいいじめで体じゆうアザができた。鬼はいつまでも鬼で逃げ回るばかりであった。
兄もいじめられたらしいが、次の年隣町の巻にある私立中学に入ったのでいじめは回避された。
習字の時間に書いた字は、うまい人は教室に先生から貼り出されるが、俺の下手な習字を(今でも下手で困っている)皆が貼り出すという精神的ないしめもあった。
先生は皆のいたずらを察していたらしく、ニヤニヤしながらそのままにしていた。このたぐいのいじめは、痛くも痒くもなく俺は平気であった。
叔父の家は旧家であるから、立派な倉がある。ある日のこと、母は倉の中で何かタンスの捜し物をしていた。
疎開した少しばかりの荷物を倉に入れさせてもらっていたからである。持ってきたはずの何かが、どうしても見つからないというのだ。
そういえば、キントキがそのあたりをウロウロしていたのを、ちらっと見たことがあったので盗られたのではないかと俺は言った。
しかし母は「思い違いもあるし、世話になっいるのだから黙っていて」と悲しそうな顔をして言った。
キントキとは叔父の奥さんのアダ名で、赤い顔をしていたので、絵本で見た昔話に出てくる熊と相撲をとったと云う金時の赤い顔を思い出してつけたものである。
しかしこの時から俺は叔母を欲張り金時と呼ぶことにした。
旧家であるから、倉の中は宝物でぎっしりなのに。この時俺は、金持ちは欲張りでケチだと思った。
日本の戦況が悪くなるにつれ、東京から学校のクラス単位で近くのお寺に集団疎開先生に引率された学童が来た。彼らはみな知っている仲間たち、楽しそうにドッチボールをする姿がうらやましかった。
俺のいる父の実家も多いと思ったあらゆる部屋、外の物置、醤油を作った土間の作業小屋などまでゴザを敷き、住みつく東京からきた疎開の人たちで満ち溢れていた。
東京は無人の街になったのだろうか?日本は勝っているのに、これは何なのだろうと驚くほどわが実家は人に満ち溢れていた。
しかしその頃(1944年~45年にかけ)東京は空襲を百回ぐらい受け10万以上の人が死んだが、負けていることは、政府が隠しニュースにもならないので皆知らないのだ。
木と紙でできている日本の家屋をアメリカは研究して、ガソリンに生ゴムを溶かしたバクダン(焼夷弾シヨウイダン)を発明した。芯の爆薬が火のついた生ゴム入りガソリンをまき散らしその生ゴムが壁などに張り付き燃えるのだ。
この火つけ爆弾が雨のように降ってくる。けなげに東京を守ろうとしていた残った人たちは火に囲まれ大多数が焼死したのだ。そんなことも知らずに、こんな都会での地獄も知らず、田舎ではのんびりしたものだ。
そんなこんなしているうちに、新潟市)の郊外に今の仮設住宅より粗末な市営住宅が出来て俺達は引っ越した。でも狭い八畳にぎゅうぎゅうだったので広く素晴らしい住み家と思えた。
家は六畳四畳半に母と子七人で寝る。もちろん風呂などない。
だが、場所は新潟市の外れで海に近く、砂防林の松原と美しい砂浜がどこまでも統く、今で言えばアウトドアーの別天地である。
所々に湧水があり、小川となつて海に注いでいる。春にはハマエンドウの花が一面に美しいエンジュ色のジュウタンになり、夏はハマヒルガオが可憐なピンクのラッパを風にそよがせ、秋にはハマスゲが綿毛の穂を風になびかせる。
冬以外はヒバリがいつも空でピイチク鳴いており、のどかなところだった。
しかしここでも俺は徹底的ないじめにあった。そのひとつが馬乗りで約数人が馬の役になり、繋がり、その上を数人が飛び乗る。
乗手が俺のところに集中的に乗るので、重さに耐えられずに潰れる。潰れれば負けで、いつまでも馬のままで乗手にはなれない。
また波打際に埋められ、かなり海水を呑まされるまで掘り出してもらえない。
女の子のスカ‐トめくりなど命令され、実行して先生に、水のバケツを持って廊下に立たされたこともあった。
やっと狭いながら我が家を得たと喜ぶのは束の間であった。
引っ越ししてたちまち食料の調達に困窮した。実家にいれば裏に畑もあり何かしらの食料、野菜のもらい受けができたが、今はそれが出来ない。
ところで、この頃は食料も少なく、僅かな配給物だけでは餓死するだけである。そこで母は足りない食料を補うべく、少ない着物を一枚ずつ持って農家をおとずれ、僅かな米や食料を得ていた。
と言っても、いまの商店に買いに行く「いらっしやい」というものでなく、恵んでやるという態度で、ひどい所では仕事のじゃまだと、竹ぼうきで追い払われた。荷担ぎとしてこんなことによく遭遇した俺は百姓が憎らしかった。
この頃は学校給食も無く、いつでもすきっ腹だ。今の子は空腹の辛さを知らないが長時間の空腹は歩くのもつらく足を一歩前に出すのも努力がいる。
水を飲んでも空腹感は満たされず、物置の土壁など崩れたところを削りだし、口に入れる。味もなくジャリジャリするがそのまま飲み込むと何か少し空腹感が癒される。
野草の新芽もよく食べた。何十回もガムのように噛んでいると少し甘く綿のようになり飲み込める。空腹感も少し和らぐが但し食べ過ぎると激しい腹痛と下痢が襲う。
その3 食うのに困り農家に丁稚(でっち)入り
食うのに困った母は、食いぶち減らしに俺を農家の手伝いとして出すことにした。小学校六年、昭和20年早春のことであった。母としては食べ盛りの子を農家で、たっぷりと飯を食べさしてやりたいと思ったのだろう。
その農家は実家の紹介で決めた。最初に疎開した和納村の近くの部落で、3町歩の田を持つ大農家だ。(1町歩は3000坪)
その頃は、戦時中という事もあり、義務教育もなく小学校ですら行かなくても良いという、いい加減なものであった。
ここに百姓の丁稚(食わせてもらうだけのタダ働き)として住み込んだ。しかし、届け出は要るらしく農家のおやじは学校へ行ってこいと言った。最初に疎開して入った学校だ。
そこで俺は一人で顔なじみの悪ガキの居る教室に入っていった。先生はびっくりし、そしてなぜか困ったような顔をして俺の名前と住所を聞いてメモをしていた。
久しぶりに逢つた悪ガキどもは、懐かしいと思ったかニコニコしていた。
農家に住み込みとなった俺は徹底的にこき使われた。朝は夜明けとともに牛に食わせる草を刈りに行く。タ方は明るいうちに帰つたらおやじに怒鳴られた。
暗くて見えなくなるまで作業をしてそれから帰るのがあたりまえなのだ。
その頃は大農家といえども、小さな田が多く耕運機も無く大きい田はせいぜい牛が引く鋤(スキ)という大きなクワのような道具があるくらいだ。
このために小さい田はクワで耕すことになり、この作業が早春にはえんえんと毎日続く。小さい田は牛も入らないのだ。小さくても300坪くらいある。それが10か所くらいあるのだ。
この作業が早春にはえんえんと毎日続く。最初の地獄が始まった。秋に刈った稲の株が残った地面、稲の根で硬くしまり耕すのに重い三本クワを使う。刃先が三本に分れた開墾用の重いクワで、小六の子供用クワなどないのだ。
その重いクワは思い切り振り上げないと地面に刺さらない。
最初は、うなるほど肩が痛んだが田に水を張る時期が迫り、あおられ夜暗く足元が見えなくなるまで作業を行った。
おやじのカーちゃんは見かねたか畑担当だが手伝ってくれた。奥さんなんて言えない黒光りする顔のゴツイ、この人は寡黙で機械のようにクワを動かしていた。いつも無口で得体に知れない人だが困る俺を見て手伝うところなど根は親切なのだろう。
この農家のおやじが且那然とかまえ小作人を使っていれば、俺も反抗しさぼったであろう。でも主人自ら一生懸命なのだ。三町歩(一万坪)の田んぼを人手を借りずに作るのだ。
しかしこのおやじ、大農家で豊かなはずだが、どけちなのである。
春から夏は売り物にならない小粒なジャガイモが味噌汁、煮ものになる、これが朝飯だ。
そして昼は冷や飯に小粒ジャガイモの具一杯の味噌汁をぶっかけた雑炊をたくさん食う。
朝昼は同じパターンなので覚えていたが夜は何を食ったか思い出せない。
マクワウリという、今のメロンの原種のような楕円,シマシマの果物は、一個も食べずに全て市場に出す。鶏を飼っていたが、もちろん卵もそうである。でも米の飯だけは腹一杯食えた。
激しい労働だ、飯はどんぶりに何杯も食う。そして力士のように体ができあがる。
他の農家は知らないがここでは食事に各自お盆に自分の茶碗とおワンを使い食べ終わったら、その器でお湯を飲み洗ったことにして各自片づける。
主婦も労働担い手として忙しいので、食器洗いの手間を省くのだ。
後で知ったが昔禅寺の食事もおかゆを食べお湯を入れてタクワンなど(漬物)でこすり洗いして食べていたとのこと。共稼ぎの皆さん手抜きのヒントがありそうですね。
俺はこの方法を山での食器洗いで実践している。食器を洗ったお湯は飲み自然の汚染もない良い方法だ。
田植えの時期は忙しく昼はデカイ塩おにぎりに漬物の食事を田んぼでする。腹がへって食いすぎると腹が膨らみ腰を折る田植え姿になるのが苦しく食うのも手加減が必要だ。でも腹がへるので吐きそうにならない限界ぐらいまで気をつけて食べる。
この頃は大きい田んぼでも人力で田植えをする。今のように田植えから刈り取りまで機械なんてなかった昔からの農法だ。
田んぼには植えるしるしを付けるため糸を張った大きいローラー形の枠を転がす。ローラーで出来た升目を五株か六株受け持ち稲苗を植える。
俺はまだ子供だ、リーチが短く四株受け持つ。
しかし植え方が浅く稲苗が浮き上がり、始めのうちは叱られた。大きい田んぼは手伝いの?誰かがやっていたらしく植えにいった覚えがない。ここは耕すのも牛の力、俺には縁がなかった。
畑には行ったことがなかったが夏になれば、いろいろつまみ食いできそうな魅力的なトマト、キユウリ、とうもろこし、があるようだ。俺が食い荒らすから出入り禁止?俺は畑の場所すら知らない。
畑に撒く肥料でこのころは人の糞尿が使われていた。これの調達のときの話だ。
この当時の化学工場は戦時中には爆薬を作るのに忙しくアメリカ爆撃機の攻撃で壊滅的な状態で、戦後も化学肥料などすぐにはできず、人間の排泄物が貴重な肥料だった。
この時隣町の吉田駅にこのトイレ排泄物をもらいに行った。大八車(1メートル位の木の車輪に鉄の輪が被せてあるリヤカー)に沢山の肥し桶(木の樽で30リットルぐらいの大きさで簡単な蓋が乗って振動で糞尿が少し漏れてクサイたる)を8本ぐらい乗せて、駅の便所に汲みにいった時のことだ。
糞尿満載で重い大八車の前で引っ張るのはあの無口のおかみさんだ。俺はうんこのこぼれる車の後を押す係だ。
土手の道に上る坂に差し掛かると、途中から傾斜がきつくなったので、登れなくなりじりじりと大八車はバックし始めた。
普通こんな場合車を道に斜めにして傾斜の負荷を軽くしジグザグに、登るがこの時土手に上がる道は狭くそんな余裕はない。俺は渾身の力を振り絞り止めようと必死だ。
その時坂の下から駆け上がってくれて、この臭いウンコの車を一緒に押し上げてくれたおばさんがいた。やっと土手の上に大八車を上げて、改めてそのおばさんを見ると都会風の服を着ていた。
東京からの疎開者だろう。でもこんな臭い車を押し上げてくれたその親切は子供心ながら涙が出るくらい嬉しかった。食うもの、住むところも不自由な時代だから人は優しくなるのだろうか?しかし俺をこき使う農家の親父、ぜんぜん優しくないなー。
でも丁稚奉公のつらさを母に言わなかったので、うまく行っていると見て、妹の富士子が食いぶち減らしのため、斜め後ろの農家へ来た。夏の頃だった。
この農家はおじいさんとおばあさんの二人だけの小さな家で、たぶんどこかの小作人と思う。しかし、この人達は、実にやさしく、自分たちの孫のように、妹をかわいがっていた。
庭で出来たマクワウリを食べさしてもらっているのが庭ごしに見える。小学校低学年の妹はウリを食べながら「兄いチャン」と叫んでうれしそうに手を振った。
もちろんこんな労働条件なので、妹の所に行ってダベってくるなんて考えられない。でも俺は妹が幸せそうなので、それで満足した。
ある日、天皇陛下の放送が有るというので、めずらしく家で昼休みしてラジオを聞いた。
このころ天皇は神様なので正座して聞かされた。もちろん休めるのでほっとしていた。
天皇のお言棄は、お経のようで何を言っているのかよく分からなかったが大人たちは日本が戦争に負けたと騒いでいた。そしてコメのうまさを知ったアメリカ捕虜が日本のコメを取り上げるなど今では考えられないことを言っていた。
俺はおやじから日本はアメリカに負けると聞かされていたが、現実になった今、まさか負けるなんて、と、かえって俄には信じられない気持ちがいっぱいだった。
やがて秋がきて米俵も背負った。今のように三十キロという袋は無く、一俵六十キロである。
今では大人も持てない人が多いだろうが、立ち上がるとき少し支える人がいればもてるよ。でも背負にくいのはカマス(ムシロの袋)に入ったジヤガイモだ。
どれくらいの重さか分からないが米俵よりは軽い。しかし、これはパッキンクが悪くゴロゴロと背負いにくい。ジャガイモが出来る初夏の頃はまだ体が出来ていなかったからかな。
日本が戦争に負けても稲刈りの秋が来る。まず早稲の稲から仕事が始まる。作業期間を分散させる為に収量は落ちるが早稲種の田んぼを少し作ってある。
早稲種の稲は丈が短く刈りにくい。
今では稲刈りはコンバインなんていう小型戦車のような機械で稲刈りされる。
稲は機械で刈り取られコメは稲穂からむしりとられ稲藁はバラバラに切られ田んぼにまかれるがこの頃の収穫方法は一株ずつ鎌で切っていくのだ。
ここで稲刈り初めての俺は大ドジをする。稲刈りの鎌で、左手の小指を切ったのだ。
稲刈りの鎌は細かいノコギリ状のギザ刃が付いているため切るとものすごく痛いのだ。
切れる刃物で切ると痛みがすくないよ!(その後の経験から)
骨に達するぐらい切れたのか?ギャーという声の後、言葉が出ない。血が止まらないのでなんかひもで縛って止血をしてくれたおかみさんに家につれて帰られる。
当然医者に連れて行ってくれると思ったがどっこい、 オキシフルという泡のでる消毒薬で傷口を洗うとホルム散という(止血薬)黄色の粉薬を傷口にたっぷりまぶしてガーゼをかぶせさらし木綿のボロを包帯にしてぐるぐる巻きつけてくれた。
このときの強烈な痛みは脳裏に写真のようにその情景とともに永遠に焼きついているだろう。
忙しい稲刈りの最中だ、医者に行くなど眼中にないのだ。
この小指の傷は二十歳くらいまではっきり付いており、今でも小指は少し曲がっている。
切った小指を使わない稲刈りなどとてもやりにくく次の日から小指は薄く包帯をして親指を除いた四本の指を布で稲束を握るかたちにギリギリ縛り痛い小指も使って作業をした。
数日は血がにじんでいたがなぜか化膿などはしないで、いつの間にか傷は快方に向かった。
本当に忙しい収穫本番では指は何とか使えた。
秋は刈ったばかりの水分を含んだ重たい稲束を運ぶ。一握り位の束ねた稲を何十束か荒縄でからげたもので、未だ子供の俺には体がミリミリきしむほど重く苦しい。
子供用の稲束などあるはずもなく大人が担ぐ重さなのだ。
しかも稲束をばらしこれをハザの上に待つ人に投げ上げるのだ。もはや余力もなく上のほうで取る人がいるとき、届かない事があるが、上からすぐ怒号が走る。
次の稲束を取りに行くわずかな時間がほっとする休息だ。夜中まで月明りの中、道に植えてあるポプラ並木に竹を渡したハザという物干しに稲を干す作業は真夜中まで続く。
一度に実りの秋をむかえるので、機械の無いこの時代、不眠不休での作業である。
重いものを運ぶ疲れ、最後の力でそれを投げ上げる。苦しくこのまま死ぬのかと思った。疲労と体の痛みで夜もなかなか寝付かれない。
つらいときはやはり家を思い出す。夜汽車の汽笛を寝床で聞きながら、あー、あれに乗れば一時間足らずで家に帰れるのに!と、いつも思っていた。
この音はつらい思いにつながり、今でもSLの汽笛は大嫌いである。あの寂しい吠えるような音は俺の心の叫びそのものだった。
死ぬかと思うほど辛かった稲の乾燥作業のハザ掛けの体験、でもこれが俺のコメへの特別な心情になる。
切り取られた稲は最後の力を振り絞り自分の茎、葉に蓄えていた残った栄養を子孫を繫栄するため子供(米粒)に回すのだ。だから天日干しに米はとてもうまい。
稲は母体、モミ(米)は母なる稲の情念がこもっている生きている生命体と俺は感じている。米粒一つでも無駄にすると稲に申し訳ないように感じるのだ。だから子供たちも茶碗についたご飯粒一つも残さずきれいに食べる。
コメには一粒づつ土、水,お天道様、の三体の神様がいると、小さい時から子供には言い聞かせているのだ。この話は丁稚で働いた農家のお婆さん(なぜか盲目の)から聞いた話だと思う。
大変な思いで作ったお米、その命をいただいて人は生きているという思いは、つらい思いをして作る米農家の共通な心と思う。ご飯を頂くときの、頂きます!は心を込めて言おう。
何も言わずに食べ始める人、ご飯を残す人などは米に対する思いやりがないのだろう。
話は飛ぶが、脱サラで始めたペンション、これから六十年後自炊の宿に切り替えたが、余ったご飯を捨てる人が絶えない。
炊飯器にこんな張り紙をしている(ご飯は我々日本人の大切な食料です。余ったらおにぎりにしてお持ち帰りか、またそのまま残しておいてください。戦後ひもじい思いをしたオーナーより)という張り紙だ。
しかしですぞ!自炊の宿を初めて十年ぐらいの間ご飯を残してくれた事は2回くらいしかない。炊飯器そっくり裏返して捨てた大量のご飯をゴミ箱によく見かける。今の人たちは、ご飯は単なる炭水化物の物質、モノと思っているのだ。
怒った米の神様、お天道様は地球温暖化の強い光で大地を焦がし砂漠化して、水の神様は大量の雨で洪水を、土の神様は肥沃な土をその雨で海に、そして人口の増加と相まって食料を得る困難が人類に来るのか、またやっと目覚めた人たちは英知で切り抜けるのか?
話を戻して、
やがて戦後、義務教育がやかましく云われるようになり、小学校も行かず、丁稚をしていることが出来なくなったので、米の収穫が終わったら家に帰ってきた。
もちろん手荷物も少なく破れかけたシャツ、拾ったモンペ(戦時中女性用の作業ズボン)これは足首が狭まり腰のところにひもで固定する袴のようなもので、作業用としてべんりだ。
このモンペという作業ズボン?誰かが川で洗濯中に流したようで川岸で拾ったものだ。まだ破れておらずしっかりしたものだ。ふしぎに俺の体形に合った。
物のない時代作業服などの支給はないのだ。ぼろ服をまとい乞食のようなスタイルで帰る俺にしかしこの農家の親父は、けちでお土産に米もくれなかった。九か月もただ働きしたのに!
こんなわずかな自分用のぼろ服が手荷物のすべてで母のもとに帰ってきた。コメが貴重なときだ。母はコメの一握りもお土産にくれればと、嘆いていた。
また米を食う人数が増え、母はどんなに米がほしかったのだろうとため息に似た嘆きの声だった。俺はなんだか申し訳ないような気持だった。
しかし俺は農家で徹底的に、こき使われたが一つもそれを恨んでいない。なぜなら、このつらさが、俺の人生に非常にプラスになったことを痛いほど知っているからなのだ。
それはつらいことがあってもあの時のつらさから比べれば何でもない、という気持ちで乗り越えらえられるからだ。